「個人種目こそ“協力”を」
体育の授業には、チームで行う種目と、
1人で行う種目があります。
短距離走、縄跳び、
マット運動、跳び箱、水泳……。
こうした“個人種目”のとき、
子どもたちはどうしても
「自分さえできればいい」と
思いがちです。
そんな姿を見るたびに、
どこか寂しさを感じていました。
体育の時間が
「自分だけの努力」で終わってしまうのが、
もったいないと思ったのです。

「学び合う体育」
現在勤務してい学校では
「1人も独りにしない」という
理念のもと、
“学び合い”の授業スタイルを
大切にしています。
体育でも、その考えをもとに
授業を組み立てています。
個人種目でも、
グループを作って活動します。
例えば短距離走では、
グループごとに記録をつけ、
「どのくらいタイムが縮まったか」
をチームで競います。
自分が速くなれば、仲間が喜ぶ。
仲間が伸びれば、自分もうれしい。
そんな関係が自然と生まれていきます。

「誰かの頑張りが、自分の喜びに変わる」
中には「もう自分は限界」と
感じる子もいます。

でも、他の子を応援したり、
アドバイスしたりすることで、
“仲間の成長”を
自分の喜びに変えられるようになります。
例えばリレーの授業では、
個人のトラック半周のタイムの合計と
リレー全体のタイムとの差を比べます。
個人の合計より速くなれば、
それは「チーム力」の証。
誰か1人だけが
速くても成り立ちません。

「どうすればもっと速くなるか?」
「バトンの受け渡しを変えてみよう」
子どもたちは、自然と考え、
工夫し、試すようになります。
「学びが“自分たちのもの”になる」
うまくいったチームの工夫を共有すると、
クラス全体のレベルが上がります。
教える側も、
教えられる側も成長していく。
そんな“共に伸びる体育”の姿が
見られるようになりました。
これまで「協力」は
チーム競技だけのものだと思っていました。
でも、“個人種目でも協力できる”ことを
子どもたちが教えてくれた気がします。

「“あの子”が動き出す瞬間」
「学び合い」という授業スタイルに出会って、
私の体育の授業が変わりました。
苦手な子も、やんちゃな子も、
クラスに馴染みにくい子も
誰かとつながることで
意欲的に動き出します。

教師の工夫ひとつで、
子どもの姿は驚くほど変わる。
その瞬間に立ち会えるのが、
体育の醍醐味だと思います。
自分だけでは感じることができない
達成感を味わせる仕組みを作っています

さいごに
子どもが自分たちで考え、
協力し、喜び合う体育。
“あの子”が居場所を見つけ、
「体育が楽しい!」と
心から言える時間を
一緒に作っていきましょう。

ちょっとでもみなさんの
授業づくりの参考になれば
私としても嬉しいです
子どもが自分たちで考えて
主体的に行動する!
体育の授業が楽しみになる!
友だちと協力することが嬉しくなる!
運動の得意な子が
苦手な子をサポートする!
子どもがいきいきする!
そんな体育の授業を
一緒に作っていきましょう!!

記事を読んでみて気になった方は
りゅう先生の
公式LINEを作成しています!!
公式LINE限定特典
無料プレゼントも配布しています
無料プレゼントの内容は…
・体育の授業の単元計画の作成方法
・体育の評価方法
・運動会で定番のあの種目の必勝法
・縄跳びの指導方法
・ティーボールの指導方法 など
の内容が入っています!
今すぐ使える内容となっていますので
公式LINEに入って
プレゼントを受け取ってください!

ぜひ活用してみてください!

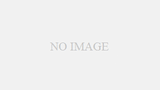
コメント